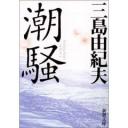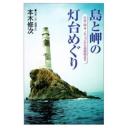和書で、ノンフィクションで、灯台にフォーカスした本というとこれまで古書を探すしかなかった中で、久しぶりに出た、いや、出てくれた灯台本です。2015年4月世界文化社刊。印刷は定評のある凸版。
前半の130ページ弱が全国100近い灯台のフルカラー写真集とその解説兼訪問記+アクセスガイドという体裁で、後半の50ページ弱に灯台にまつわる歴史やトリビアなどがわかりやすくまとめられています。
どの灯台の写真も思わず引き込まれるような美しさですが、それらはすべて写真家でもある著者が全国の灯台を渡り歩いて1つ1つ丹念に撮影したもの。いや、「丹念」というレベルではなく、途方もない労力の成果と言うべきでしょうか。
灯台というのはたいてい陸上からは到達しにくい場所にあり、全国各地の灯台を訪れるというだけでもかなりの努力を強いられます。この本のアクセスガイドにも「・・・下車、徒歩約1時間30分」などという記述が平然と並んでいます。氏の場合、現地に着き、灯台を撮影する構図をいろいろと試行するのはもちろんのこと、「灯台が美しく見える瞬間」までひたすら待つ、ということを繰り返されていたようです。
よく晴れた日の日中、青い海、緑の山と白い灯台というのももちろん美しい絵ではありますが、当然のことながら日中は灯台は光りません。かといって夜になってしまうと、灯台の写真を撮っても光しか写りません。いわゆる黄昏時、昼と夜との境界のとき、灯光と灯台が同時に美しく見える一瞬が切り取られてこの本に凝縮されているといえるかもしれません。
先日、たまたま氏とお会いする機会があったのですが、「灯台が点灯する瞬間」が好きだ、と仰っていました。なるほど。
この本の価格は1800円(税別)となっていますが、灯台好きの人にとっては安すぎる価格かもしれませんね。
ニッポン灯台紀行(岡克己) はコメントを受け付けていません
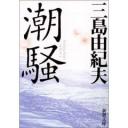
灯台、または灯台守が主題というわけではなく、灯台や灯台守がモチーフの1つとして描かれている本を上げていけばきりがないような気もしますが、この本については、是非とも取り上げたいと思って書いています。
三島文学の中では特異な位置付けの本らしいのですが、そのあたりの解説はググるといくらでも出てくると思いますので省略します。また、何度も映画化されていますので、映画をご覧になったかたも多いかもしれません。実は私は映画は見ていないので、あくまでも本を読んでの感想です。
とにかく、描かれている景色も、社会も、そして登場人物の全てが「清浄」なのです。もちろん、純愛小説で、主人公の2人の逢瀬を妨害する相手たちとの喜怒哀楽などもあり、貧しい島での所帯じみた描写も多くあります。が、登場してくる人たちの全て、悪役も含めて全ての人たちが、まぶしいくらいにまっすぐで、正直なのです。
自然と共存し、神を信じ、人を疑うということをしない。いくつか印象的な表現を書き抜いてみますと、まず、屈強な海の男である主人公、新治の、神社での祈り。漁の豊穣や、島の人々の幸福、母や弟の健康をまず一生懸命に願い、最後に、おそるおそる初恋の彼女のことをそっと願う。そして「こんな身勝手なお祈りをして、神様は俺に罰をお下しになったりしないだろうか」と心配するような男なのです。
また、新治の母の描写にも「・・・突堤まで行って波の砕けるさまを眺めた。彼女もまた息子と同じように、ものを考えるときには海に相談にゆくのである。」というくだりもあります。
西洋の小賢しい文明に晒される前の、古代の太平洋の島々の出来事だといわれても素直にうなずけそうな社会であり、人々なのです。以前読んだ大人向けの童話で、池澤夏樹の「南の島のティオ」という、ミクロネシアを舞台にしたこれまた純白な小説があるのですが、読後感はそれに近しいものがありました。
そして、それらの清浄な風景の中に実にしっくりと溶け込んでいるのが、島で最も眺めが良い2つの場所の1つとして描かれている燈台なのです。物語のラストは、島中の皆に将来を祝福された2人が、燈台長の案内で燈台を見学するシーンです。燈台の持つ、「清浄さ」というイメージが存分に生かされた小説のような気がします。
解説などを読むと、舞台になった歌島というのは、伊勢湾に実在する「神島」という島なのだそうです。この島は、取材に来た三島が川端康成に送った手紙で「目下、神島という一孤島に来ております。映画館もパチンコ屋も呑み屋も、喫茶店も、すべて『よごれた』ものはなにもありません。この僕まで浄化されてー。ここには本当の人間の生活がありそうです」と伝えているように、少なくとも、小説の書かれた50年前は、小説の舞台と同じ社会が実在していたようです。
一度、訪れてみたいような、訪れてはいけないような。
潮騒(三島由紀夫) はコメントを受け付けていません

成山堂書店の「交通ブックスシリーズ」、長岡日出雄著。初版発行が平成5年12月となっていますが、その初版のまま、現在(2008.1)でもamazonで買えました。
15年間も売れなかった本、ということになるので、あまり内容に期待は持てないか・・・?と思いましたがさにあらず。大変、中身の濃い、読み応えのある本でした。
著者の長岡氏は官僚出身。第3管区海上保安本部長、海上保安庁灯台部長、さらにはIALA(国際航路標識協会)の会長まで歴任した人のようですが、「灯台」に対しての思いいれはアマチュア並に強いようです。
灯台の歴史、灯台にまつわる文学作品や映画、灯台守の話など薀蓄に満ちた話も多いですし、現代の灯台について、その技術やサービスについての解説もあります。灯台放送に関する記述は、このサイトの別の記事でも引用させていただきました。
普通の解説書では、「それは海保でこう決められている」というような事実の解説が多いですが、著者の場合、航路標識や灯台業務に関するさまざまなルールを「制定する側」の立場で、実際にさまざまなルールを作って来られた経験にもとづく話は、なかなか他では読めない話かと思います。
灯台について色々知りたい、というかたには必読書かもしれません。
日本の灯台 はコメントを受け付けていません
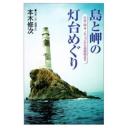
日本一の「島博士」本木修次さんの著書。ハート出版。
副題が「日本一周、ノサップから波照間まで」とあるよう、日本列島の端から端まで、233もの灯台への訪問記です。各灯台のスペックを詳しく知るための解説書ではなく、実際に訪問しての印象を中心に記述されています。
だいたい、灯台というのは地形的に「端っこ」になっている場所にあるため、辺鄙な場所や、離島などに設置されていることが多く、簡単に訪問できる場所ばかりとは限らないようです。この本の中にも、小船をチャーターしたり、けものみちのような道を分け入ったりという、訪問というよりも探検に近いような記述もたくさん出てきます。
私がつくづく感心したのは、著者の本木さんというのは、決してコレクター的なマニアではないという点です。時々見かける「JR全駅制覇」みたいなコレクター的なマニアは、駅が好きというよりも、チェックリストの塗りつぶしに快感を覚えるようで、一度経験した場所は、「もうそこは経験済み」ということで見向きもしないことが多いようなのですが、本木さんの場合、実に50年以上をかけて、辺鄙な場所の灯台にも「何度も何度も繰り返して」訪問されているのです。
灯台に対する愛情と熱意のなせる技なんでしょうね。
ただ、それぞれの灯台についての訪問記自体は、感情移入が強すぎて、少し引いてしまう人もいるかもしれません。ほとんどの灯台を「すらりとした美人」「かわいい娘っこ」「日本健児」などと擬人化しているという点もその1つです。
また、表現自体が例えば「帰り道はもう腹ぺこ、くたびれ。でも両側は絶壁の細い道、用心、用心。」というように、他人に読ませているのか自分に言い聞かせているのか不分明な記述になっているところが多々あるのも、引っかかる人は引っかかるかもしれません。
ただ、日本には本当にいろんなバリエーションの灯台があり、とんでもなく辺鄙な場所に設置されているということを、改めて認識させてくれる貴重な本です。もちろん、実際に灯台を訪問する際のガイドブックとしても役立つのも間違いありません。一読の価値ありです。
表紙の写真の灯台は、「新:喜びも悲しみも幾年月」にも登場した、水の子島灯台です。
島と岬の灯台めぐり はコメントを受け付けていません
 暁教育図書というところから出版された、「日本発見」シリーズの第35巻。発行は昭和57年という、消費税導入以前の古い本ですが、今でも古書店やオークションサイトなどでわりとたくさん流通しているようです。
暁教育図書というところから出版された、「日本発見」シリーズの第35巻。発行は昭和57年という、消費税導入以前の古い本ですが、今でも古書店やオークションサイトなどでわりとたくさん流通しているようです。
とにかく内容が濃い。濃すぎるくらいです。巻頭特集の納沙布岬をはじめ、いわゆる灯台紹介の記事も多いですが、『岬の文学散歩』というコーナーでは岬や灯台をモチーフとして書かれた、井上靖や太宰治、庄野潤三ら多くの作品が紹介されています。
かたや「オリエンタルホテルの灯台悲願」や「洋式灯台の移り変わり」などの解説風読み物も豊富。男木島灯台(瀬戸内海)に勤務中(当時)の灯台守夫妻への取材記事もあれば、岬とか灯台にまつわる民話や伝説も収録されています。歴史記事としては、洋式灯台創設の立役者となったブラントンや、初代燈台頭となった佐野常民の紹介などもあります。
用語辞典や年表、年中行事、「岬と燈台全国ガイド」などもまとめられており、これ1冊で岬と灯台に関するポータルサイトができあがりそうなくらいです。
もちろん25年も前の本なので、GPSを前提とした現代の灯台のありかたとは方式論などが異なる部分もありますが、今読んでも充分に楽しめる1冊です。機会があれば図書館でも良いので一度手に取ってみる価値ありと思います。
ちなみに、表紙のまぶしい灯台は佐田岬灯台のようです。(先日まで佐多岬と書き間違えてました、スミマセン)
岬と燈台 はコメントを受け付けていません