やぎしり(北海道:2007.11)
■通報内容:(毎時52分の状況)
神威岬灯台:波の高さ
積丹岬無線方位信号所:風向速気圧
焼尻島灯台:風向風速気圧
■出力:50W
■受信報告書宛先:留萌海上保安部交通課
■受信確認証の確認内容:氏名、証明日付。
牧場に隣接した灯台というのは珍しいですね。
■通報内容:(毎時52分の状況)
神威岬灯台:波の高さ
積丹岬無線方位信号所:風向速気圧
焼尻島灯台:風向風速気圧
■出力:50W
■受信報告書宛先:留萌海上保安部交通課
■受信確認証の確認内容:氏名、証明日付。
牧場に隣接した灯台というのは珍しいですね。
先日、南房総の沖ノ島灯台、洲埼灯台、そして野島埼灯台をたずねたときの記録です。
1:プラン
JR東日本が、館山周辺のバス券もついた「南房総フリーきっぷ」というのを発売しており、船橋からだと5500円。これはずいぶんオトクかな・・・と思っていろいろ調べていると、館山から各灯台へ行くバスの便というのが非常に悪い。特に平日だと絶望的だということが判明。また、今回行こうとしている沖ノ島灯台など、クルマがないとどうしようも無い場所のようなので、電車で行っても結局、館山駅でクルマを調達しないといけない。
逆に、今年(2007年)7月、館山自動車道と富津館山道路を結ぶ君津ICと富津中央IC間が開通。館山までクルマで一気に行けることになったということもわかり、結局最初からレンタカーを借りて行くことに。
2:館山到着
 富浦ICは高速の富津館山道路の終着点。ここから127号線に入るのだが、まず驚くのが道路の両脇に並ぶやしの木。
富浦ICは高速の富津館山道路の終着点。ここから127号線に入るのだが、まず驚くのが道路の両脇に並ぶやしの木。
なんだか別の国に来た気分になる。まず目指したのはJR館山駅。ここで噂のくじら弁当を調達。1日限定30個の販売で、11時頃に到着した時点で残り8個。なんとかセーフ。
3:沖ノ島灯台
沖ノ島というのは、館山の南西、海上自衛隊の航空基地から海に向かって伸びた砂洲の向こう側にある。普通のクルマで砂洲を渡るのは無理なので、いったんクルマを降り、くじら弁当を携えて沖ノ島まで歩く。

島全体が鬱蒼とした森になっており、入ってしまうとあまり「島」という印象が無いが、森を抜けたところにとても可愛らしい灯台が建っている。プレートを読むと『初点昭和46年1月』とあるので、結構新しい。頂上には太陽電池パネルらしきものもある。
 沖ノ島全体は公園としても整備されているようで、ピクニック用のテーブルもそこかしこにあったり、森の中のトイレは太陽電池パネルの屋根で結構清潔。海辺のテーブルで大変おいしくくじら弁当を食させていただきました。
沖ノ島全体は公園としても整備されているようで、ピクニック用のテーブルもそこかしこにあったり、森の中のトイレは太陽電池パネルの屋根で結構清潔。海辺のテーブルで大変おいしくくじら弁当を食させていただきました。
また、平日ということもあってか、私たち夫婦以外に訪問者は皆無。青色、というよりは藍色に近いくらい晴れ渡った空、青い海、白い灯台、緑の森。すばらしい目の保養になった。

フランスのブルターニュ地方に実在する、ル・ジュマン灯台を舞台にしたせつない物語。
1963年、アルジェリアからの負傷帰還兵、元時計職人のアントワーヌ(グレゴリ・デランジェール)が、新人灯台要員としてジュマン灯台に着任する。ブルターニュ地方というのはかなり排他的な土地柄であったようで、灯台守の人々や土地の男達からはずいぶん冷たいあしらいを受けてしまう・・というところから本編が始まる。
政府が帰還兵のために用意してくれた選択肢は他にも財務局勤務など、ラクそうなものが色々あったにもかかわらず、アントワーヌが「好き好んで」最果ての地の灯台勤務を志願したというというのはアントワーヌの心の傷がなせる業だが、同時に、灯台というものが「心に傷を負ったものが行くべき場所」というイメージもあるのかもしれない。
調和の取れた田舎の生活、いわば感情の振幅があまり大きくない生活に慣れ親しんでいた人たちの中にアントワーヌという異邦人が入り込んだことが触媒になり、人々の感情の振幅が増大されてしまう。
その結果、それまで「心はひとつ。同じブルターニュ人」とお互いに思っていた人たちの中でも、異邦人を排除したい者たちばかりではなく、実は田舎の閉塞感に辟易していたことを自覚する者も出てくる。やがて、アントワーヌと友情を結ぶイヴォン(フィリップ・トレトン)、アントワーヌと恋に落ちてしまうマベ(サンドリーヌ・ボネール)は後者の典型だ。しかしイヴォンとマベは仲睦まじい夫婦でもあったのだ。
大変に繊細な映画で、ラフなストーリーを書いてしまうと興醒めかもしれないので、内容の紹介は以上にとどめる。もう少し詳しく知りたい人は実際に映画を見ていただくのが一番だが、2005年に日本で公開されたときの公式サイトを今でも見ることができるのでそちらを参照されたい。
とにかく驚くのはジュマン灯台の立地。なんと海の中に灯台だけがにょっきりと屹立しているのだ。船着場なども無く、要員交代は灯台からロープを垂らして行う。波風が強いときなどは、灯台に辿りつくことがすでに命懸けだ。(さすがに1991年からは無人化・自動化されたと映画の中で出てくる)
また、妙なところで興味を引かれてしまったのは、灯台守は休めない、気を抜けない仕事であると同時に日中の無聊を持て余す仕事でもあるという点だ。この映画ではイヴォンが勤務中に意味無く何十脚もの椅子を作り続けるシーンが出てくる。分刻みで刺激を求め続けることが多い現代人は、こんな環境に放り込まれると正常な精神を保つことが難しいかもしれない。

1986年の松竹映画、監督は前作と同じ木下恵介。主演は加藤剛と大原麗子。
前作が、生活感あふれるシーンが多いにもかかわらず全体にどことなく透明感が漂っていたのに対し、本作はリアルな現実感がある。
もちろんこれは前作の時代背景が戦前・戦中・戦後であり、現代人からすると別の世界の出来事であるかのような錯覚に陥るからであろうが、もうひとつ、登場する灯台の景色が左右している部分も大きいと思う。
前作では、石狩灯台とか女島灯台など、そこで生きていくこと自体がすでに大きな試練であるかのような灯台が強烈な印象を残した。過酷な生活に耐え切れずに亡くなってしまう婦人、戦争中に標的とされた灯台で殉職した人たちなど、「死」というモチーフもそこかしこに登場してくる。
しかし本作では、石廊崎、八丈島など、全体に明るいイメージの灯台が多いのだ。大原麗子の演じる「おしゃべりで明るい奥さん」もそのイメージを増幅している。大ざっぱにまとめると、本作は、前作ほどの厳しさは無く、「ちょっとしんみりするホームドラマ」ということになるのかもしれない。
ただ、灯台好きな人にとっては興味が尽きないシーンが多い。
石廊崎で加藤剛がデスクに向かって放送する灯台放送。「各局、各局、各局、こちらは、いろう、いろう、いろう。海上保安庁が、石廊崎灯台の、気象状況をお知らせします」という、聞き慣れた?フレーズが映画に登場してくるというのもちょっと嬉しい。
今でこそ大阪ハーバーレーダー以外は全て合成音声になっているが、昔は各灯台から、映画に出てきたような、こじんまりした放送施設を使って手作り放送していたのだろうなと思うと感慨深い。
また、豊後水道沖の孤島に聳える水の子島灯台。前作では遠景だけが登場し、船からそれを眺めるきよ子(高峰秀子)が夫(佐田啓二)から、「あんな灯台(に赴任するというのは)どうだ?」と問われて「ぞっとするわ」と答えていたが、本作では実際に水の子島灯台で仕事をしている男たちのシーンも登場する。
それ以外にも数多くの灯台が登場するが、前作で登場した灯台とほとんど重なっていないというのも色々と新しい発見ができて面白い。

中国製のラジオで高性能のものはいくつかあるようですが、中でも有名なのがここでご紹介するdegen(德劲)社のDE1103というラジオです。(ワールド無線で9,800円。送料別)
「DE1103」でググると山のように記事がヒットすることからも、このラジオのユーザーが多いことがうかがえます。しかしなんといってもこのラジオを有名にしたのは、『例の裏技』かもしれません。(裏技を転載するのは気が引けますので、気になる人は『DE1103 裏技』とかでググってみてください。
とにかく、裏技を施すことによって、
(1)0kHz~30,000kHzまで連続受信が可能。
(2)中波でも内蔵バーアンテナを切り離して外部アンテナモードにすることが可能。
という、ちょっとした通信型受信機のような真似ができるのです。
もちろん、基本性能も良く、1665kHzの海上交通情報が1669kHzで聞いている灯台放送に混信したりすることもありません。音質もまあまあだし、RECOUT端子も付いています。別の項でご紹介しますが、FMの感度の良さも半端ではないようです。
強いて難点を挙げれば、デザインがイマイチ。(好みの問題でしょうけど)。大きな液晶ディスプレイに放送バンドがごちゃごちゃ表示されていますが、アナログラジオでは無いので、ほとんど無意味です。また、音量調節がチューニングダイヤルと同じ、というのは、ずいぶん長く使っている今でもやっぱり馴染めません。また、チューニングは「1kHz単位」なので細かい調整も可能ですが、逆に言えば1kHz単位でのチューニングしかできないので、例えば558kHzのラジオ関西を聞いたあと、1669kHzの灯台放送を聞こうなどと思うと、結構、指の運動になります。メモリを活用しないと、素のままではしんどいですね。
しかし、繰り返しますが性能は抜群で、このラジオとループアンテナの組合せで、全ての灯台放送が受信できたのはもちろん、『いろいろな気象放送』や、『中短波で聞く海外放送』でご紹介している放送など、実に色々な放送が受信できました。これだけの性能のラジオが1万円未満で売られているわけですから、ラジオ放送に興味がある人にとっては大変オススメであることは間違いないと思います。
先日、「日本の灯台」(長岡日出雄)という本を読み、灯台放送の意外な一面を知ることができました。
灯台の業務というのは僻地の勤務であることが多く、灯台守の人たちが家族共々赴任して業務に従事するというのは、大変に苛酷なことであったようです。また、戦後、海上保安庁管轄の灯台が激増したこともあり、限られた予算で多くの灯台の管理を行なっていくためにも、「灯台管理の自動化、無人化」は極めて切実な課題でした。
昔、光源として石油などを燃やしていた頃ならともかく、戦後であればほとんどの灯台は電力を用いていたため、いわゆる「光の点滅」については、自動化はさほど難しくはなかったようです。もちろん、自動化即無人化となるわけではなく、障害発生時のスムーズな対応や、障害の未然防止のための定期点検業務などがきちんと運用に乗る、という大前提が必要なので、組織や設備の再編などは大変な仕事だったようです。
しかし、なかでも灯台業務の自動化を遅らせたのが、実は灯台放送などの『付帯業務』だったようなのです。付帯業務の1つとして、昔、各灯台では「船舶通報業務」という業務も行なっていました。これはまだ船舶無線が普及していなかった時代に、無線設備を持っていた灯台が、沿岸航行中の船舶と船主・代理店などの間での入出港情報を仲介したり、通航船舶名をロイド協会に通知したりしていたという仕事で、どう考えても「人手」によるやりとりが必須でしたが、この業務は1964年頃には廃止されたようです。
そしてもう1つが灯台放送(船舶気象通報)業務なのです。通報のほうだけであれば、現在でも実施されている音声合成システムを使うことでなんとかなるのですが、問題は、各灯台で行なっていた気象観測業務のほうでした。灯台での気象観測の歴史は古く、明治初年から行なわれていたようです。岬や島などの気候は内陸部とは異なることが多く、気象庁のデータを補完するためにも重要な意味があったようです。
また、波高やうねりなど、気象庁データでは入手できない局地的な情報に対する船舶からの要望も多く、1950年代から、現在に近い状態での「船舶気象通報」が始まったということです。
風向風速気圧といった測定項目は、素人目にも、なんとなくすぐ自動化できそうな気がしますが、波高、うねり、視程、といった「目で見てナンボ」の世界の自動化は、テクノロジーの発達を待つ必要がありました。現在では、レーダーを用いた波高の測定や、レーザーを用いた視程の推定が行なわれているようです。
最後の有人灯台であった女島からも、灯台放送が流されていましたね。
長いこと私は、灯台は気象庁の管轄だと信じていたのだが、実は海上保安庁の管轄であったのだ。(最近知った)。気象庁というのは、たしか池澤夏樹が著書の中で「国の役所の中で汚職とはもっとも縁が薄いイメージだ」と書いていたが、全く同感だ。海上保安庁の管轄であると知ったときはちょっとショックだった。
ただそのときはもう1つ誤解していて、海上保安庁というのは海上自衛隊のいるところだと思っていた。実はそうでなく、海上自衛隊は防衛省の管轄で、海上保安庁というのは気象庁と並んで国土交通省の管轄だったのだ。(これはもっと最近知った。防衛庁が防衛省になったというニュースのとき)
・・・ということは灯台はやっぱり気象庁の仲間?いやいやそうでなく、海上保安庁の英語名は Japan Coast Guard。アメリカのCoast Guard(沿岸警備隊)と同様、武力も保有している。
個人的には、沿岸警備は防衛省、灯台業務は気象庁としてくれたほうが落ち着くのだが。
・・・・という記事を以前の書きかけブログのほうに書いたところ、コメントをくれたかたがいらっしゃって、そのまま転載すると、
=================
沿岸警備まで防衛省がやっちゃうと違法漁船や密輸密航取締りすら軍事行動と受け取られて、国際問題になる危険があります。また、海保が海賊対策として東南アジアで行っている各国支援も軍事援助と非難されてしまうでしょう。
実を言うと、灯台も国防上重要な施設なんです。もちろん航路を維持するためのものですが、戦時中は爆撃機を察知して空襲警報を発していたりしていたので、米軍から攻撃を受けてなくなった灯台職員の方もかなりいます。現代でも、一部の灯台は不審船監視の任務があるとか。海外では、灯台を海軍が管轄しているところも多いですね。民間団体が管理している場合もありますが、気象機関の管轄というのは聞いたことがないです。あくまで観測所ではなく航路標識ですから。
=================
・・・と、「なるほど、そういうことでしたか」と、ひとつ賢くなったのですが、例えばアメリカと較べるとちょっと違うのかなと思えることもあります。
「海を守る灯台業務」は海上保安庁の仕事だとしても、灯台放送というのは、船舶気象通報という名のとおり、正味、気象情報を伝えています。これは、気象庁の発表した情報を伝えているのではなくて、実際に、灯台に「象測器」を置いて、気象観測もやっているのです。
アメリカの場合はどうかというと、灯台を管轄しているのはCoast Guard(沿岸警備隊)で、これは日本と同じ。というか、日本がアメリカと同じ。しかし、Marine Forecastと呼ばれる船舶気象通報は、NOAA(国立海洋大気局。日本の気象庁みたいなものかな)が全て統括しているようで、あまり灯台とは関係なさそうなのです。
まあ、どうでもいい話といえばどうでもいい話ですが。。。

私はマンション住まいなので、ラジオの受信環境としてはあまりよろしくありません。おまけに室内には妙に家電製品が多くて、ノイズだらけ。特にプラズマテレビは最悪です。どうしても外部アンテナのお世話にならざるを得ません。
幸いマンションとはいえ1階で、気持ち程度に庭もあるので、そこにアンテナを立ててみることにしました。(右上の写真)私はアマチュア無線家ではなく、電気工学、電波工学系の知識も全く持ち合わせていないのですが、単純な共振回路で理解できるループアンテナなら自作できるような気がしたわけです。(まあ、ありがちな安易な発想だとは思いますが・・・・)

 アンテナ枠の素材を何にするか、どう固定するかなど、色々と日曜大工的な失敗を繰り返しながら、最終的に落ち着いたかたちが、表題の4連(4回巻きという意味ではありません)ループアンテナなのです。落ち着いたとはいえ、素人工作の悲しさ、ずいぶん不恰好で見苦しいですが・・・・
アンテナ枠の素材を何にするか、どう固定するかなど、色々と日曜大工的な失敗を繰り返しながら、最終的に落ち着いたかたちが、表題の4連(4回巻きという意味ではありません)ループアンテナなのです。落ち着いたとはいえ、素人工作の悲しさ、ずいぶん不恰好で見苦しいですが・・・・
で、なぜ4連か?最初に作ったのは、もちろん1連(1つのLC回路)のシンプルなアンテナでした。狙いは灯台放送だったので、あまり同調範囲を広くする必要も無く、2回巻で充分同調できることがわかりました。(同調範囲は1400kHz~2600kHzくらいでした)。
アンテナ線には単芯の皮膜銅線を使っていたのですが、それまでも色々な失敗を繰り返していたおかげで、山のようにアンテナ線が余っていました。「処分するのも勿体無いな・・・、どうせだし、もう1つアンテナを作ろうか。ん?待てよ、2つ作って一緒につなげば感度も倍になったりして。」と、イージーに考え、まず作ったのは2連のアンテナ(それぞれ2回巻)でした。
ところが、驚いたことに、発想はイージーでしたが、明らかに1連のアンテナよりも感度が向上しているのです。さらに驚いたことには、同調範囲が1300kHz~3300kHzと、ぐーんとワイドになってるじゃありませんか。(なんで??)
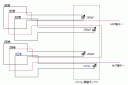 この発見?に気を良くして、アンテナを一気に4連とし、そのうちひとつは欲を出して低い周波数にも同調できるようにと、容量の大きなエアバリコンについないだ5回巻としてみた、というのが現在の姿なのです。
この発見?に気を良くして、アンテナを一気に4連とし、そのうちひとつは欲を出して低い周波数にも同調できるようにと、容量の大きなエアバリコンについないだ5回巻としてみた、というのが現在の姿なのです。
5回巻の部分を単独で実測してみると、同調範囲は440kHz~1030kHzくらいと、やたら低いほうに偏っているのですが、4つ全部つなぐと、440kHz~3400kHzくらいまで、各バリコンの調整次第で連続的に同調できるのです。アンテナ同士がピックアップコイルの部分も合わせて何か相互作用しているんだと思いますが、ほんとに、なぜなんでしょうね???接続図は右のとおりです。
 バリコンの調整には、右のようなバリコンボックスを作ってまとめてみました。灯台放送とその周辺だけであればあまり大きくバリコンの調整をすることはありませんが、周波数を大きくあちこちするような聞き方をするときは大変です。。。
バリコンの調整には、右のようなバリコンボックスを作ってまとめてみました。灯台放送とその周辺だけであればあまり大きくバリコンの調整をすることはありませんが、周波数を大きくあちこちするような聞き方をするときは大変です。。。
とにかく、このアンテナのおかげで、灯台放送についていえば、「みやこじま」以外の28局は、程度の差こそあれ毎夜聞こえるようになりました。また、週に1度くらいは「みやこじま」も何とか、放送内容が聞き取れる程度に聞こえてくれます。(今が冬だからかもしれませんが)
しかし、調子に乗ってローテーターをつけたり、さらにモノのついでにとFMアンテナまで乗っけたりして、やたらと時間をお金を消費してしまいました。DE1103が4~5台買えたかもしれません。(笑)
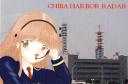 灯台放送(船舶気象通報)は文字通り、気象情報に特化した放送ですが、海上保安庁が、全国7ヶ所の海上交通情報センターなどから放送している海上交通情報の中でも気象状況がアナウンスされています。もちろん、「交通情報」がメインなので、大型船の入出港情報など、普段聞けない情報が多くて面白いです。周波数は、局によって異なり、1665kHz・1651kHz・2019kHzが使用されています。
灯台放送(船舶気象通報)は文字通り、気象情報に特化した放送ですが、海上保安庁が、全国7ヶ所の海上交通情報センターなどから放送している海上交通情報の中でも気象状況がアナウンスされています。もちろん、「交通情報」がメインなので、大型船の入出港情報など、普段聞けない情報が多くて面白いです。周波数は、局によって異なり、1665kHz・1651kHz・2019kHzが使用されています。
■1665kHzでの定時放送スケジュール
毎時00分~:東京湾海上交通センター(東京マーチス)
名古屋湾海上交通センター(名古屋ハーバーレーダー)
毎時15分~:伊勢湾海上交通センター(伊勢湾マーチス)
犬吠埼船舶通航信号所(鹿島沿岸情報)ただし04時~19時台のみ。
毎時30分~:東京湾海上交通センター(東京マーチス)
名古屋湾海上交通センター(名古屋ハーバーレーダー)
毎時45分~:伊勢湾海上交通センター(伊勢湾マーチス)
——————–
偶数時45分~:本牧船舶通航信号所(京浜ハーバーレーダー)ただし、05時~20時の間のみ。
奇数時45分~:東京13号地。ただし、05時~20時の間のみ。
偶数時52分30秒~:塩浜船舶通航信号所(京浜ハーバーレーダー)ただし、05時~20時の間のみ。
奇数時52分30秒~:千葉船舶通航信号所(千葉ハーバーレーダー)ただし、05時~20時の間のみ。
・・・とにかく、同一時間帯に2種類重なっているので聞きやすいとは言えません。
その上、この1665kHzという周波数は潮流信号所も使用しているので、下手をすると(うまく行くと?)さらに重なります。
■1651kHzでの定時放送スケジュール
毎時00分~:備讃瀬戸海上交通センター(備讃マーチス)
関門海峡海上交通センター(関門マーチス)
毎時15分~:大阪湾海上交通センター(大阪マーチス)
来島海峡海上交通センター(来島マーチス)
牧山船舶通航信号所(洞海ハーバーレーダー)ただし04~19時台の偶数時。
毎時30分~:備讃瀬戸海上交通センター(備讃マーチス)
関門海峡海上交通センター(関門マーチス)
大阪湾船舶通航信号所(大阪ハーバーレーダー)ただし04~19時台のみ。
毎時45分~:大阪湾海上交通センター(大阪マーチス)
来島海峡海上交通センター(来島マーチス)
■2019kHzでの定時放送スケジュール
毎時00分~:伊勢湾海上交通センター(伊勢湾マーチス)英語。
毎時15分~:名古屋海上交通センター(名古屋マーチス)英語。
毎時30分~:伊勢湾海上交通センター(伊勢湾マーチス)英語。
毎時45分~:名古屋海上交通センター(名古屋マーチス)英語。
・・・自動合成音声で放送しているようなのですが、ものすごく癖のある英語です。聞き取りにくいこと夥しい。「各局、各局」という呼びかけは、ここでは「All stations, All stationsとなります。
ちなみに。マーチスとはmaritime information service(海の情報サービス)のことで、東京湾海上交通センターを設置したとき海上保安庁燈台部(現交通部)電波標識課の職員が発案したのが語源とのことです。
出典:海上保安庁用語辞典
↑ただし、スペルミスでmaritimeがmarintimeと表記されています。
このサイトの「灯台放送全局紹介」では、それぞれの局の発行しているQSLカード、あるいはレターを添えてご紹介しています。このQSLカード、綺麗に印刷された絵葉書のようなものもありますが、多くはインクジェットプリンターで都度印刷された手作りの味わいがあります。また、灯台をあしらったデザインというのは実に「絵になる」魅力的なものです。私はQSLカードのコレクターではありませんが、灯台放送のカードだけは唯一、「欲しい」と思ったカードでした。
そんなQSLカード(受信確認証)を入手するにはどうするか?
まずは、灯台放送を受信して、受信報告書を書きます。当たり前ですね。
灯台放送の放送時間は1局あたりせいぜい1~2分なので、放送された全文を書き取って送るのが具体的で良いかもしれません。「えりも」局や「げさし」局など、実際の放送原文と照合して、放送原文までつけて返送してくださったりするところもあります。
次に、「切手を貼った返信用封筒」を同封して、管轄の海上保安本部交通課に送ります。
ここで注意しないといけないのは、海上保安部交通課の業務は、決してQSLカード発行が主たる業務ではないということに配慮することです。『受信報告書を送ったのだからQSLカードを返送してくれて当然だろ?』というような態度は慎みましょう。返送までにかかる期間もさまざまです。私の場合も、一番早いところは受信報告の送付後僅か3日ほどで返信をいただけた局もあれば、2ヶ月くらいかかったところもあります。
余談ですが、灯台放送の受信報告書の宛先は、現在と数年前とでは全く異なります。
昔は、灯台放送を聞いたときの受信報告書の宛先は、灯台が立っている地域の航路標識事務所でした。今でもググると、それらを宛先として指定するような記事もヒットしてきますのでお間違えなきよう。
しかし2007年現在、一部の例外を除いて航路標識事務所は存在しないのです。
これは、海上保安庁が平成13年度(2001年)からの5カ年計画で、全国74箇所(当時)の航路標識事務所を各地区の海上保安部へ統合したことによります。
現在では、受信報告書の宛先のほとんどは、管轄区域の海上保安部の交通課です。ですので、「いろう」と「はちじょうじま」、「むろと」と「あしずり」などは同じ宛先になります。具体的な住所はこのサイトの最上部のメニューにつけておきましたので参考にしてみてください。
Powered by WordPress